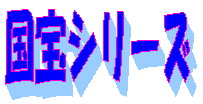■唐招提寺御影堂に安置されている。1951年指定。脱活乾漆造り、彩色。像高80.1cmである。天平宝持7年(763)の作。
■唐招提寺御影堂に安置されている。1951年指定。脱活乾漆造り、彩色。像高80.1cmである。天平宝持7年(763)の作。
■わが国肖像彫刻の最古の作品である。像の高さは当時の肖像彫刻の中では、やや小さめで、これがむしろ鑑真その人の大きさであったと思われる。
■和上は座死することを願ったというが、この像には死のイメージは見えず、明らかに瞑想している生気が感じられる。そして、静かに目を閉じている表情のその奥に、瞑想内にある澄みきった世界を思わせる。
■この坐像の各部には和上の個性が感じられる細やかな表現や、独自の自然な非対称が見られ、きわめて対看写照に近い形で造られたものであることをうかがわせる。
■また、着衣についても丁寧な表現がなされている。右肩を覆っている偏杉、背中から右肩後方の半分を覆い左襟の線を作る横被、左肩部から腹前にかかる袈裟という三枚の衣がみられ、偏杉や袈裟は自然な衣紋線が表されるが、横被にはなく、衣の質感を変えているのである。
■角ばった顔立ち、左右で微妙に形を変える目、先のとがった鼻、薄い唇などからは忠実に写実したもと思われる。そしてこの顔立ちと唇からは不屈の意志の強さが、閉じられた目からはその慈愛が、鼻からは禅定における静かな息づかいと発達した嗅覚が、そして眉間の皺と眼窩のくぼみからは渡海の苦労が各々読み取れる。<五度失敗、67歳の渡日>
 ◆御影堂◆
◆御影堂◆
◆境内の北側に位置する土塀に囲まれ、ひっそりとした瀟洒な建物。元は、興福寺の別当坊だった一乗院宸殿の遺構で明治以降は県庁や奈良地方裁判所の庁舎として使われたものを昭和38年(1964)移築復元したものです。
現在は、鑑真和上坐像(国宝)が奉安されており、昭和46年から57年にかけて東山魁夷画伯が描かれた、鑑真和上坐像厨子扉絵、ふすま絵、障壁画が収められています。
◆東山魁夷画伯奉納御影堂障壁画◆
◆鑑真和上坐像が安置される御影堂内の襖絵です。日本を代表する画家、東山魁夷画伯が、10年を超える歳月をかけ、鑑真和上に捧げた大作です。日本の風土をテーマとして、色鮮やかに描かれた「山雲(さんうん)」「濤声(とうせい)」と、墨一色で描かれた和上の故郷中国の壮大な風景「揚州薫風(ようしゅうくんぷう)」「黄山暁雲(こうざんぎょううん)」「桂林月宵(けいりんげっしょう)」のほか、坐像を収めた厨子の扉絵「瑞光(ずいこう)」も画伯の作です。
唐招提寺は、南都六宗の一つである律宗の総本山です。多くの苦難の末、来日をはたされた鑑真大和上は、東大寺で5年を過ごした後、新田部(にたべ)親王の旧宅地(現在の奈良市五条町)を下賜されて、天平宝字3年(759)に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場を開きました。