 ■大宝蔵殿にあり、1952年11月に指定された。銅造、鍍金、像高86.9cm、7世紀末頃の作とされる。
■大宝蔵殿にあり、1952年11月に指定された。銅造、鍍金、像高86.9cm、7世紀末頃の作とされる。
■童子のそれを想わせる手指の形や独特の甘いやさしさをふくむ表情が印象的な像である。
■18世紀に法隆寺の僧・良訓(りょうきん)が著した『古今一陽集(ここんいちようしゅう)』には、宝永7年(1710)に東院絵殿(えでん)の内陣に仏壇を作ってこの像を祀ったこと、そしてこの像に祈ると、悪夢を善夢に転じてくれるとの霊験により「夢違(ゆめたがえ・ゆめちがい)観音」の名で信仰を集めたことなどが記されている。
■それ以前の詳細は不明であるが、元禄7年(1694)に新たに鋳造された台座の銘文から、当時すでにこの名が流布していたこともわかる。
■像は、左手に持つ小瓶を含むほぼ全体を蝋型の一鋳(いっちゅう)で造り、足?(あしほぞ)で台座に固定している。中型(なかご)は頭部から裳裾までおおむね外形にそって設けたと思われるが、型持(かたもち)が見えず、また両足の間の裳裾下底部が閉じられて中型の土が内部に残る「くるみ中型」の形式がとられている。
■このほか、三面頭飾(さんめんとうしょく=頭部の正面と左右の飾り)や冠帯、天衣の一部など別鋳とする部分も多く、そのスマートな造形と手際のよい技術がマッチした、白鳳時代という金銅仏全盛期の像であることを示している。
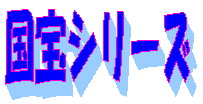
NO.08
法隆寺/観音菩薩立像(夢違観音)
■画像や紹介文はホームページ/wikipediaなどから借用しました■
| ホームページへ | 国宝シリーズトップへ | 次のページへ | 前のページへ |