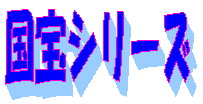■東院の「夢殿」にあり、1951年6月に指定された。樟(くす)材、一本造、金箔押、像高179.9cmであり、7世紀前半の作とされる。
■東院の「夢殿」にあり、1951年6月に指定された。樟(くす)材、一本造、金箔押、像高179.9cmであり、7世紀前半の作とされる。
■大きな山形の金銅透彫(こんどうすかしぼり)の宝冠をかぶり、胸前に両手で宝珠を捧げて立つ。
■『東院資材帳』には、「上宮王(かみつみやおう)等身観音菩薩木造壱驅金箔押」すなわち上宮王(聖徳太子)と身の丈が等しい木造の観音像であり、金箔押で仕上げられる旨が記されている。そこから、太子在世中に作られた御影とも、太子の現(うつ)し身(=肖像)とも伝えられている。
■この像が「救世観音」と呼ばれるようになるのは、平安時代に入り『聖徳太子伝暦』などが、太子の本地として、この観音を位置づけて以降のことと思われる。
 ■またこの像は、12世紀前半にはすでに秘仏として逗子内に安置され、中・近世を通じて人びとの眼から長く閉ざされてきていたが、明治17年(もしくは同19年)に「岡倉天心」と「フェノロサ」によって開扉され、その姿が一般に知られるようになった。
■またこの像は、12世紀前半にはすでに秘仏として逗子内に安置され、中・近世を通じて人びとの眼から長く閉ざされてきていたが、明治17年(もしくは同19年)に「岡倉天心」と「フェノロサ」によって開扉され、その姿が一般に知られるようになった。
■頭体のプロポーションは、腰帯がやや上で結ばれるため、一見下半身が長く感じられるが、実際には絶妙なバランスを保っている。肩を引いて下腹部を少し突き出し、全体に「く」の字形を表すような側面観も、他の像の類似的なそれとは異なり、余分な力がぬけた人体の、ごく自然な立ち姿を示す。
■正面で左右対称に広がる天衣も、その自然な側面観に心地よい視覚的リズム感を与えるように、斜め後方へ、実に伸びやかに流れている。
■そして慈愛に満ちた表情がある。しばしば写真などでは、その顔立ちは「デモーニッシュ」とでも形容すべき不気味な厳かさをのぞかせることもある。しかし、自然な光のもとで仰ぐそれは、写真からの印象とは異質で、人びとの心の深奥を静かに見つめ、そっと救済の手をさしのべる菩薩の表情にほかならない。
■こ聖徳太子が実際にそうであったかはともかく、この像の造形には、太子の人なりや思想をそのようにとらえ、理想化して後世に伝えようとした作家の限りない想いがうかがえよう。
≪救世観音が祀られている≫
……「フェノロサにより見出されるまで、白衣でぐるぐる巻き
にされた秘仏であったのは何故か?」……
■…………………………………………………………■
■明治時代(18884年)にフェノロサによって見出されるまで数百年の間、白衣ぐるぐる巻きの秘仏とされ、フェノロサが白布を解く時に寺僧達は悉く逃げ出したと伝えられている。
■この像には怨念や祟りと関係があったものと思われる。そもそも夢殿はなんの目的で作られ、救世観音はなんの目的でここに安置されたか?
■通説では行信僧都が739年に聖徳太子を供養するため再建された法隆寺の横に東院伽藍(上宮王院)を建てそこに八角仏殿(夢殿)を建立したとある。これだけでは何故その中に祟りと関連するような救世観音が祭られているか判らない。
■「夢殿と救世観音は聖徳太子の祟りを鎮めるため作られた」梅原猛氏は「隠された十字架」の中でこう述べる。
■法隆寺再建の年次はわからない(多分710年初め?)が夢殿は建立された年次が明確でありこれが重要なヒントである。この時代は時の大政治家であった藤原不比等の娘宮子の産んだ首(おびと)皇子が724年聖武天皇となり、不比等の4人の息子も重要な官職につき藤原全盛の世であった。
■ところが、737年この4人の息子が当時大流行した天然痘のため全員がほぼ同時に死んでしまったのである。これは聖徳太子の祟り(太子一族は罪なくして藤原氏に滅ばされた)以外にないということで翌々年739年夢殿を建立し太子の祟りをしずめるべく救世観音を作ったのだと梅原氏はいう。
■救世観音の頭と胸に釘が打ち込まれている。頭の後ろの光背は通常は背中から支えるのが普通だが、救世観音はなんと頭に直接釘で打ち込まれている。頭に釘が打ち込まれている仏像など聞いたことがない。絶句!胸の部分の十字の木組みの真ん中にも釘が打ち付けられているという。