 ■法隆寺は古くは斑鳩寺と称し、聖徳太子が自身の宮殿、斑鳩宮の隣接地に、推古天皇13年から15年(605-607~)ごろ建立した寺である。
■法隆寺は古くは斑鳩寺と称し、聖徳太子が自身の宮殿、斑鳩宮の隣接地に、推古天皇13年から15年(605-607~)ごろ建立した寺である。
■法隆寺の釈迦三尊像は、正式呼称を「釈迦如来及び両脇侍像」といいます。
■1951年6月に国宝に指定されました。法隆寺の金堂に安置され、銅造、鍍金造りです。中尊は像高87.5cmで左脇侍が92.3cm、右脇侍は93.9cmです。製造年は、推古天皇31年(623)とされています。(止利作)
■金堂の本尊として、法隆寺創建の当初から安置されてきたことがはっきりしている貴重な像である、といわれます。
■この像は連弁形の大後背を背にした三尊で、いわゆる一光三尊の形式である。当初は後背の周囲にさらに別製の飛天のようなものが付き、上下絶妙な構成であったとみられる。
■また、その杏仁形(きょうにんぎょう)の眼や口元にアルカイックスマイルを浮かべる神秘的な風貌、ほぼ左右対称の正面観照性を基調とする全体観、そして細部にわたる形態のシャープさなど、像のすみずみまで厳格で崇高な精神性がうかがえる。
■また、その懸裳や着衣のスタイルは、中国の6世紀前半に確立したものをほぼ継承しているが、この像においては、それらにみられない変則的な要素も指摘され、作者の図様決定にいたる苦心がうかがえる。(中国様式を受け継ぐ曲線美)
■焼失後に再建された金堂の内陣は、聖徳太子の冥福を祈る釈迦三尊を中心に、向かって右に薬師、左に阿弥陀を祀る三つの空間で構成されている。
■この構成が堂本来のあり方かどうかは、なお疑問の点もあるが、再建当初の位置づけをそのまま伝えるとすれば、そこには、聖徳太子を中心に、父・用明天皇と母・間(はし)人皇后の菩提を弔う、初期の太子信仰の俤(おもかげ)を想定することもできる。
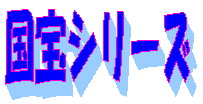
NO.06
法隆寺/釈迦三尊像
■画像や紹介文はホームページ/wikipediaなどから借用しました■
| ホームページへ | 国宝シリーズトップへ | 次のページへ | 前のページへ |