 ■木造で高さは約195cmで、九世紀中頃の作である。金堂に安置され、19852年11月に指定された。
■木造で高さは約195cmで、九世紀中頃の作である。金堂に安置され、19852年11月に指定された。
■本体は中尊の薬師如来より小さいが、なお等身を超える法量(寸法)がある。両手を除いて榧(かや)の一材から彫出し、頭上を一列に廻る十面や両腕も継ぎ目をつくらないように丸彫りとしている。
■彫刻を優先して彩色は塗りの層を薄く色合いの軽い簡素なものとし、きわめて洗練された彫技によって美しい翻波式衣文や弾力ある肉付きを表現している。
■しかし、薬師如来像とは違って頭と手が小さく腕が細く、腹を包み込むように腰を張り出したプロポーションは、うら若い女性を思わせる。
■頬の膨らみや頭体の深い奥行きに特色のある奈良後期以来の様式を受け継ぎながらも、作者は自らの鋭い観察によって、少女のあどけなさを残す顔立ちと初々しく豊かな肢体の女性の姿を造り出したのである。
■意外なことに、その女性が妊婦であることまでも見て取ることができる。とろんとした目つき、上気した息遣いが観じられるような口元、お腹を突き出して肩を引く不安定な姿勢など、懐妊していることを写実的に表現することを求められたのであろう。
■若い女性の姿と懐妊、この二つの主題は、薄い銅板を切り抜いて作られた当初の装身具によっても繰り返される。額の上には、野に摘む花で作ったような可憐な飾りが、子を宿す腹には、標的のように大きな輪宝が懸けられている。
■こうしてみると二つの主題が意味するのは、やはり現実の人間の姿と祈祷の対象であった。中尊の薬師如来像に取り入れられた二つの様式が表現するものと全く同一ということになる。
■作製された経緯に注目したい。嘉承三年(850)の宮廷の状況がそれである。仁明天皇の病深刻になり、延命を祈る修法が連日行われたが、当時貴族の筆頭にあった右大臣藤原良房の娘、明子が次の文徳天皇を皇太子となる惟仁親王(清和天皇)を出産した。それまで、良房は、天皇の祖父となる望みを実現するために仁明天皇の延命と娘、明子の出産の両方を必要としていたのである。この造立が良房によって図られた可能性は高い。
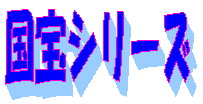
NO.05
室生寺/十一面観音立像
■画像や紹介文はホームページ/wikipediaなどから借用しました■
| ホームページへ | 国宝シリーズトップへ | 次のページへ | 前のページへ |