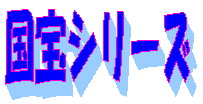■奈良時代の名作、国宝・十一面観音で有名な聖林寺は藤原家の氏寺、妙楽寺(現、談山神社)の別院として創建された古刹です。古い伽らんを尽く失っていますが、それでも天平以降各時代の仏像、仏画を今に伝え、本尊には子授けの祈願仏、霊験あらたかな大きな石地蔵をお祀りしています。門前からは卑弥呼のお墓とも言われる箸墓などの古墳を含む大和盆地の東半分と山辺の道、三輪山を一望のもとにできます。古き御仏を拝観し古代の歴史・文化に想いをはせる格好の地といえましょう。
■寺全体が懸崖作りのような、崖に石組みを施した上に建っています。小さな山門を入るとすぐに本堂です。本堂には本尊の地蔵菩薩が祀られていますが、その容姿には少し驚かされます。
■十一面観音は、本堂からさらに階段を50段ほど上がった上の観音堂に安置されています。辺りの景観に溶け込んだ趣のある御堂の中から、訪れるものにやさしいまなざしを投げかけます。あたかも千年以上もそこに立ちすくんでいたかのように、静かに佇立しています。
■十一面観音は、よく知られているように、かつては三輪山・大御輪寺の本尊であった。大御輪寺は奈良時代の中頃、大神々社の最も古い神宮寺として設けられ、十一面観音はその本尊として祀られてきたという。明治になると神仏分離・廃仏毀釈の嵐が吹き荒れるが、既に幕末はその前触れがあったのであろう。十一面観音はじめの三体の仏像は慶応四年五月十六日、大八車で三輪からこの地に避難された。果たして、廃仏の波は三輪の神宮寺を呑んで、凡ての仏教関係の物は破壊し尽くされた。本尊の観音様がどのようにして、何のために祀られてきたか、今となっては知る由もない。観音さまに関した書類凡てが灰燼に帰したからである。当時聖林寺の住持は大心和尚であった。和尚は三輪流の十一面観音法(この観音さまの拝み方)の伝授を受けた唯一の人であり、観音さまは三輪流神道の正嫡が住む寺に移られたのである。