「高浜虚子」について
|
NO.04
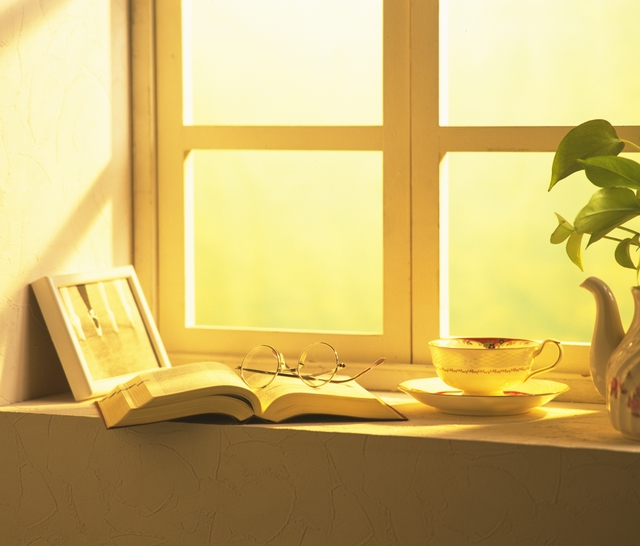
|
■虚子が足かけ四年に亙小諸での疎開生活を切りあげた折の句。『句日記』によれば、「十月十四日。長野俳人別れの為に大挙し来る」とあり、掲出句の他に「荷造りもせずに火鉢や対応す」「蒲団荷造りそばに留別句会かな」「風吹いて慌ただしさよ秋の蝶」「松茸の荷がつきし程貰けり」の四句が録されている。 ■山本健吉は、「昼の星」とは太白星(火星)であるとし、「菌」は紅天狗茸か月夜茸で、どのみち色彩の鮮やか毒茸の類であろう、とする。また二つの異様な色彩のものを対置し。抽象的な装飾画のように、ただその二つのものが並べ置かれているだけである、とした。 ■大野林火は同じく薄暗い山中のこととし、魑魅妖怪のごとく真っ赤な菌、真っ黄色の菌と天上の爛々と輝いている昼の星をデモニッシュなものと捉える。 ■金子兜太は「そこにはギョッとするような冷徹な、いわば『白痴美』すらあった。これほど人間を抹殺できる人物の実体は何なのだろう。」と虚子との距離を強調する。 ■それに対し虚子の直弟子、清崎敏郎は「属目の松茸から、想飛躍して行った。その松茸の生えている茸山の姿が、先ず脳裏に浮かんだ」とし、同じく湯浅桃邑は「発想動機が奈辺にあったか?或いは悠々と遊んでゐたのかも知れない」という。 ■これらの論を整理する形で、川崎展宏の論はある。川崎は近代俳句の鑑賞の限界を示唆しつつ、作句の場を「留別句会の席上で遊んだのである」とする。 ■さらに近年では村松紅花が当日の同席者として、座中に「深い井戸を覗くと、昼でも星の見える話」が話柄に上ったことを証言しつつ、虚子の句もそれによるとした。さらに宮坂静生は「爛々」はやはり天体の恩愛である、とする。 ■私見を最後に付け加えるなら、清崎説に与しつつ虚子の脳裏には丹波竹田の西山泊雲の茸山が浮かんでいたのではお想像している。詳述する紙幅はないが小諸時代と泊雲の没年との関係による。 |
| ホームへ | 読後トップへ | 次へ | 前へ |