 ■興福寺の阿修羅像は、734年(天平6)に建立された西金堂に造立安置された八部衆のうちの1躯です。 阿修羅は「アスラ」という古代インドの神が仏教に溶け込む中で生まれた「戦いの神」。そのため本来は、恐ろしい表情をした像が多くみられました。
■興福寺の阿修羅像は、734年(天平6)に建立された西金堂に造立安置された八部衆のうちの1躯です。 阿修羅は「アスラ」という古代インドの神が仏教に溶け込む中で生まれた「戦いの神」。そのため本来は、恐ろしい表情をした像が多くみられました。
■しかしながら興福寺の阿修羅像だけは若く精悍な顔立ちで、物憂げな表情をしています。 興福寺の阿修羅像は「脱活乾漆像((だっかつかんしつぞう)」です。
「脱活」というのは、「張子の虎」のように内部が空洞と言う意味。
■そして「乾漆」というのは「漆が乾いて堅くなった」と言う意味です。 その像容は、身体に条帛と腰裳のみをつける「三面六臂」の異形です。
■筋肉を削ぎ落としたような細身の体は腰が高く、繊細で優美な姿をしています。 左右両面は、眉を寄せ、唇をかみしめ、やや厳しい表情をしていますが、正面の表情は眉を少し寄せる厳しさの中に、爽やかな美しさを感じます。胸前の合掌手から、仏教に帰依した阿修羅を表現したものと思われます。
■興福寺の阿修羅像は、天平6年(734)、光明皇后(こうみょうこうごう)が信仰していた「金光明最勝王経」という経典が基になり、光明皇后の母、橘三千代(たちばなのみちよ))の一周忌供養の菩提を弔うために造像されたものです。
その「金光明最勝王経」に記された「懺悔の教え」が影響を与え、「心の葛藤」を表現した人間に近い顔立ちになったと言われています。その時代は天変地異が相次ぎ、不治の伝染病にも怯えていた時代でした。
■そんな時代戦乱や大火など幾つもの災難を、興福寺の阿修羅像は乗り越えてきました。
興福寺像は、阿修羅像の遺品のなかでも比類なき逸品です。 見る人間が暗く沈んだ気持ちで見れば、その表情は暗く見えるかもしれないし、また華やかな気持ちで見れば凛々しく爽やかさを感じることでしょう。
また心に何か負い目を感じていれば、それを見抜かれそうな恐れを感じるかもしれません。 そう、興福寺の阿修羅像は、見る人の心を映し出してくる仏像なのです。
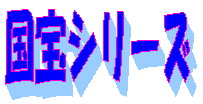
NO.01
阿修羅像
■画像や紹介文はホームページから借用しました■
| ホームページへ | 国宝シリーズトップへ | 次のページへ | 前のページへ |